「ルシア・ベルリンの小説は帯電している。むき出しの電線のように、触れるとビリッ、バチッとくる。」最終章のあとの文章でリディア・デイビス氏の『物語こそがすべて』という文章の中に書かれています。
また、あとがきの中で、訳者の岸本佐知子さんは「一読して打ちのめされた」とも書いています。この小説を読んだ私は一体何を感じたのか、24の物語を読み終えた今、改めて思い返してみました。
『エンジェル・コインランドリー店』

これは私が初めて読んだ彼女の作品です。
主人公の女性が通うコインランドリーで出会う人々との些細なやりとりを描いているのですが、その表現は「生き生きと」というより、常に「死」を思わせるところが物語全体の雰囲気を作っているように感じます。
この感覚は、『エンジェル・コインランドリー店』だけのことではなく、24の物語全体に感じる感覚でした。
「もしあたしが木曜に来なかったら、それはあたしが死んでるってことだから、悪いけどあんた死体の発見者になってちょうだい」と彼女に言ったのは、ランドリーの客の女性。その言葉のとおり死んでしまった。
「神よ我に勇気を与えたまえ。ベビーベッド新品未使用 赤ちゃん死亡につき」と書かれていたのは、店の壁の張り紙。
こんな具合。
ただ、「死」を思わせるといっても、「死」を感じさせつつも、その「死」に向かって必死でもがいている登場人物たちの姿に引き込まれていく、そんな思いが残ります。
『沈黙』

吐き出すような思いの延長に、本来なら誰にも知られたくない、人の本心をえぐり取り、晒しものにするような場面があります。
それは『沈黙』という物語の中でのやりとり。
「私は恥ずかしさに打ちのめされてうなずいた。でももっと恥ずべきは、あのとき自分が考えたことだった。ジョンにもそれがわかったのだろう。彼はこっちがちゃんと頭で理解できていない、ましてや口に出していないことを、いつも見抜いてしまう」
ジョン叔父は主人公の心の中にあり、表には出てくるはずのない感情を言葉にして無理やりに引っ張り出し、本人に叩きつける。
「・・・お前は妹のことを妬んでるんだ・・・」。
主人公は自分ですら自覚していない、妹への妬みを鋭い言葉で突きつけられる。
こんなやり取りのなかで、作者は現実の世界では決して語ってこなかった本当の気持ちを、登場人物の口を通して語っているのだと思います。
『さあ土曜日だ』

私が24の物語のなかで一番好きなのは『さあ土曜日だ』。
主人公は刑務所の囚人。
CDと呼ばれる刑務所仲間のことについて主人公が
「奴に読書に目覚めさせたのはおれだった。奴が初めて言葉と恋に落ちたのは、スティーヴン・クレーンの『オープン・ボート』だった。」
と語るくだりが好きです。
この後、主人公はCDを刑務所の中の文章クラスに誘います。
べヴィンズという文章クラスの先生がその都度、生徒たちにテーマを与え、文章を創る。
そのやり取りのなかで囚人たちは自然と自分の心の中を表現し、成長していきます。
特にCDの文章には輝くものがありました。ベヴィンズ先生はCDのことをこう語っています「オーケイ、白状する。教師をやっている人間なら誰でも経験あることだと思う。
ただ頭がいいとか、才能があるだけじゃない。魂の気高さなのよ。それがある人は、やると心に決めたことはきっと見事にやってみせる」と。
ただ悲しいのはこの物語がハッピーエンドではないこと、CDに明るい未来がやってこなかったこと。
『さあ土曜日だ』をなぜ自分が一番好きだと思うのか、それを一言でいうと、光がさしているから。
その光は囚人たちの成長。文章クラスの中で自分をオープンにし、成長していく姿。相変わらず重たいストーリーの中で、その姿を光と感じるから好きなのだと思います。
まとめ
物語をいくつか読み進めていくと、登場人物や場面が重複していることを感じます。
それはこの24の物語全部が、作者であるルシア・ベルリンの人生そのものだからなのでしょう。
キーワードは「鉱山」「アルコール中毒」「刑務所」「教師」等々。
自分の人生と重ねているからこそ出てくる「吐き出すような思い」「吐き出すような言葉」。
その思いや言葉を受け止めたとき、読者はその言葉に感電するのでしょうね。
24の物語その一つひとつについて語っていくときりがないのですが、24の物語をとおして、その比喩の多さには驚かされます。
「彼女の小説は直喩の宝庫だ。」と語るのは、前述のリディア・デイビス氏。
ただ残念なのは、その比喩を自分がイメージしきれないことです。
もしこの本を読んでみようと思うなら、いつもよりたくさんの時間を用意してください。
決してななめ読みするような本ではない、私はそう思います。
リディア・デイヴィス
アメリカ合衆国の作家で、とくに短編小説で知られる。1976年に最初の作品集『第13番目の女』を刊行。1987年に発表した作品集『分解する』で名声を得た。
ホワイティング財団文学賞(1988)、ラナン文学賞(1998)、アメリカ芸術文学アカデミー功労賞(2013)、マン・ブッカー国際文学賞(2013)等を受賞(Wikipediaより)
岸本佐知子
翻訳家。訳書にリディア・デイヴィス『話の終わり』『ほとんど記憶のない女』、ミランダ・ジュライ『最初の悪い男』ほか
2007年『ねにもつタイプ』で講談社エッセイ賞受賞


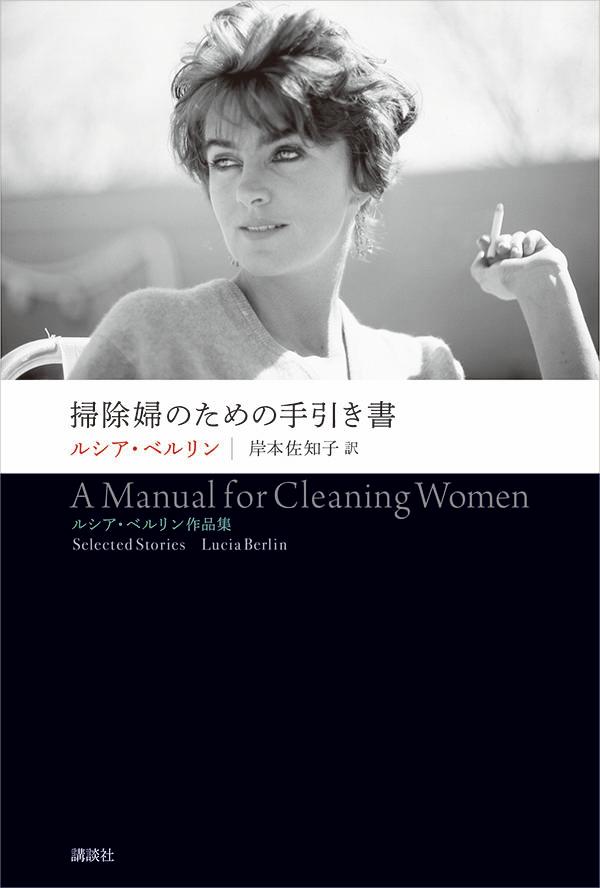

コメント